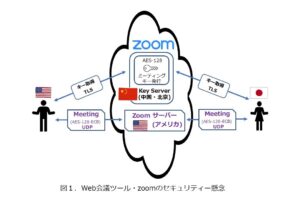表面工学の歴史的背景と今後の展開
材料・表面工学研究所
特別栄誉教授・顧問 本間 英夫
めっき産業近代化のルーツ
昭和21年、関東学院大学の前身である工業専門学校に、学生の技術習得と、学生に働き場所を与えることを目的として、実習工場がスタートした。昭和23年には、工場内に関東学院技術試験所が併設され、昭和26年に私立学校法の改正にともない、教育事業のほかに学校経営を支える収益事業ができるようになり、独立採算性の事業部が立ち上がった。
昭和28年には通産省からの助成金の交付を受け、関東自動車、トヨタ自動車向けのめっき加工の生産に入った。その後は、トヨタ自動車工業と技術交流が開始され、大学発の研究開発として多大の評価を受けるようになった。その技術は中村実先生(JAMFの設立者でハイテクノの初代社長)が、大学に赴任される以前から横浜市職員として光沢青化銅めっきの技術を開発され大学の事業部の指導をされていた。その後、昭和31年に機械科の講師として赴任され事業部のめっき工場の品質は大いに高まり、トヨタ自動車のバンパーのめっきは産業界から高い評価を受けていた。また先生は、経験と勘に頼っていた作業を、最新の技術を導入して綿密に分析管理を行うことにより、良品率を飛躍的に増加させた。したがって当時から分析管理や評価のための実験室が整備されており、機械科の助教授を経て昭和35年に教授となり工業化学科の設立に尽力された。事業部の部長と工業化学科の教授を兼務され技術スタッフとの総力で昭和37年に世界に先駆けて、プラスチックス上のめっき技術に成功し、表面処理業界にとっては一大革命をもたらした。現ハイテクノ顧問の斉藤先生は、当時の事業部に籍をおき、横浜国立大学の大学院でプラめっきのキーテクノロジーである無電解銅めっきの基礎研究に着手された。今、盛んとなってきている社会人国内留学の走りである。
そのときに提唱された『混成電位論』は、まさに無電解めっきの析出を理論的に明快に解析したもので、この研究成果に対して、当時関連学会から理論の提唱に関して論文賞を受賞している。また光沢青化銅めっきでは技術賞が受賞され、表面処理分野では大きな評価を上げるようになり国内はもとより、アメリカでも大きな反響があり、マスコミでも大きく報道された。
私は昭和39年に二期生として卒研に配属されたが、当時はプラめっきがスタートしたばかりでトラブルが続き、配属された卒研生のうち3名は大学で研究をし、多くは杉田の神奈川県工業試験所で研究を行うことになった。
私自身は工業試験所で卒研を行った後、大学に戻り専攻科・大学院へと進んだ。その間、先生は多忙を極め、ほとんど卒研生と私の間で研究が進められた。このように中村実先生は工業化学科の設立に尽力され、また大学事業部部長を兼務され世界に先駆けてプラスチックのめっきの実用化に成功しさらにはプリント基板製造にも大学の事業部でとし着手するようになる。そのころから大学のキャンパスでは手狭なので北久里浜に4800坪の工場用地を購入し移転も始まった。このような背景からめっき業界のトップの支援の下に本学に工業化学科に続いて、めっきの関連学科を作る構想が進んでおりこの種の構想が着々と進められ、当時の理事長坂田佑先生が了解済みで、白山源三郎学長と中村先生との間で、めっき学科を中心とした第2工業化学館の設立の確約書まで出来ていたのである。このことに関しては、現在の本学のトップは誰も知らない。
(注)ほとんどだれも知らない話がもう一つ。経営学の父と言われたピータードラッカーが1960年頃2、3度キャンパスにあった白山先生宅を訪れ、キリスト教の普及状況、日本の文化を調査された。当時、本学の事業部でトヨタ自動車のバンバーのめっきを行っていた関係で、トヨタのトップからの要請でドラッカーが本社を訪ね「職業改善プログラム」を提案し、一挙に生産性と品質の向上に繋がったとのことである。
更にはアメリカに今も現存するNAMF(National Association of Metal Finishes会員数数千社の協会)の日本支部(JAMF当初会員数50社程度)を昭和40年スタート。教育事業としてめっき上級講座を東京のお茶の水でスタートされた。当時は最新鋭の視聴覚教育の設備を導入し毎年50名以上の受講者が熱心に受講した。私は第一回めっき上級講座が始まった年は大学院の学生で、講義内容の概要をまとめて会員企業にお送りする、いわゆる書記役を担当、したがって表面処理に関連するトップの先生方の講義を受講できたのでその後の研究開発に非常に役立った。私が助手に任命された昭和42,3年ころから学園紛争が激化し本学ではキャンパス内にめっき工場を持っていたので学生は「産学協同路線反対」とキャンパスをロックアウト、国道16号線にバリケードを張るに至った。ほとんどの先生は毅然とした態度が取れず、紛争は過激さを増し、学生との話し合いでは解決の糸口は全く見いだせなかった。中村先生は機動隊導入を勇断して教授会でアピールし、紛争は解決した。
しかし残念ながら、それを機に昭和45年くらいだったと思うが、先生は大学を去ることになる。先生が47歳の時であり、私はまだ助手で28歳の頃であった。その後、先生は大学院教授として籍を残され、先生の指導の下、研究室を運営することになる。
私が助教授から教授になった頃から、工業化学科の中に実装や表面処理を中心としたコース、または研究所を作ってはとの要請を、産業界からたびたび受けてきた。大学の研究所ではこれまで、プラめっきに始まり、環境問題にいち早く着手し、続いてコンピューターを用いた化学制御を研究、さらにはプリント基板の一連の化学プロセスから実装領域に展開し、今では半導体の成膜プロセスまで研究するようになってきている。また当時から大学でハイテクノの講座を行えば大学の修了証書が出るので重みが出ると提案する人もいた。
これまで関東学院大学の伝統と他の大学に無い特徴を守り、さらに発展させねばと、必死になって産業界からの協同研究、委託研究や公的研究機関他大学との連繋を実施してきた。産業界から,学会から、他大学から、公的機関から注目してくれていたので現在は研究所が立ち上がっているがハイテクノの教育事業を大学が継承するのがいいとの判断になってきた。
歳を取ると私を含めて、どうしても現状維持で、余り急激な変化を好まないのであるが、それにしても今回は絶好のチャンスである。
実はその後NAMFは教育にそれほど熱心でなかったので日本支部のJAMFはNAMFから脱退、現在のハイテクノとして教育事業が継承されてきた。この講座は現在のハイテクノの教育事業でありすでに今年で53回生を送り出すことになり、表面処理業界では認知度高く経営者トップ、技術者の幹部候補生が受講。これまでの受講修了者2100名程度である。
実現に向けての具体的な行動
先に述べたように、中村先生が50数年前に表面処理学科を作る構想から実際に大学上層部と化学館を作る確約を取り、具体的に行動しようとしていた矢先に、学園紛争が激しさを増してきたのである。特に、当時はすでに事業部ではバンバーの金属めっきの他に、世界に先駆けてプラめっきの技術を立ち上げていたので、国内は勿論のことアメリカ、台湾、韓国から見学者が殺到していた。
プラめっき技術の延長線上として、現在はエレクトロニクス製品の全てに使われている、プリント基板の製造プロセスも確立されようとしていた。
大学の「人になれ奉仕せよ」の校訓を着実に守り、実行し、特許は取らず、全国から訪ねてこられた技術の方々に、詳細にわたってお教えした。
また、その事業部はキャンパスの中に500名を越える従業員を抱えていた。製造や技術に携わっている若い人たちの多くは、昼働き、夜は工業化学科、機械工学科、電気科などで学んでいた。産学協同の最も理想的なシステムが本学にあったのである。
しかし、何度も繰り返しになるが、この理想的な大学の運営方式は、当時の世界的に吹き荒れた学園紛争、学問とはなんだ!に始まり、特に本学では日本唯一の工場を持つ大学であったので、産学協同路線反対の狼煙が巻き起り、実現寸前のめっき学科の設立構想を断念せざるを得なかったのである。
先生の心中はいかばかりか。先生が自信を持って、この構想を実行に移すところまで来た背景には、昭和30年後半から40年代の工業界の成長期と呼応していた。
先生は、アメリカの表面処理工業会のブランチを日本に作られ、会員企業は全て、主だった表面処理企業から構成されていた。定かではないが100社くらい会員企業になっていたと思う。その方々から、表面処理の学科を作って欲しいとの要請が強く、またその際は全面的にサポートするとの確約を頂いていたのである。しかしながら、「本間おまえは大学に残れ、俺は中小企業の育成にほかの方法で取り組む」と、大学を去られたのである。その後たまには大学に足を運んで、後輩に檄を飛ばしてください、実際の実験の様子を見て、コメントくださいと何度も要請したが大学を去ってからは、一度としてキャンパスを訪れなかった。ものすごい思い入れがあり、社会情勢の中で自分の思いが実現できなかったことが悔しかったのであろう。
今こそ規模は小さいが、その何分の一でもいいから、実現しなければならない。
繰り返すがその時期は今しかない。 本学でめっき関係の学部のコースの立ち上げとハイテクノの事業を継承する時が来た。今までの伝統から、是非実現しなければならない。ただのオフィスのフロアーがあるだけでは意味が無く、大学のキャンパス内にはめっきを中心とした表面工学コースを設け、毎年学生を受け入れるような体制の構築を要請している。表面処理の業界は日本に3000社(現在は1500社)近くある。ハイテクノの上級講座を本学で継承することによりさらに講座が充実するであろう。